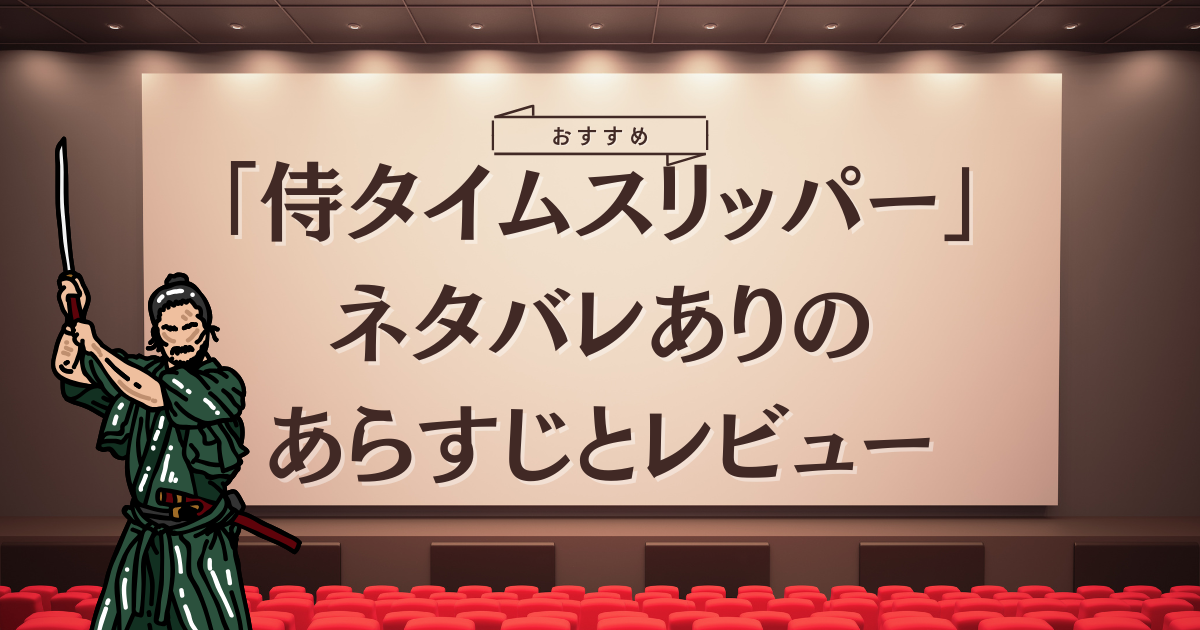近年、低予算ながらも口コミで人気に火がつき、異例の大ヒットとなった映画「カメラを止めるな!」。2024年8月17日に公開された日本映画「侍タイムスリッパー」もまた、自主制作映画ながら、多くの映画ファンを虜にし、興行収入2億円を突破する異例のヒットを記録しています!!
そしてとうとう2025年第67回ブルーリボン賞では「侍タイムスリッパー」が作品賞に、主演の山口馬木也さんが主演男優賞に選ばれ見事2冠を達成しました!!

この記事では、そんな「侍タイムスリッパー」のあらすじをネタバレありで詳しく紹介するとともに、作品の魅力やレビュー、そして監督や制作陣に関する情報まで徹底解説していきます!!
「侍タイムスリッパー」の基本情報
映画『侍タイムスリッパー』は、幕末の会津藩士が現代の時代劇撮影所にタイムスリップし、斬られ役として新たな人生を歩む姿を描いたコメディ作品です。本作は、低予算の自主制作映画でありながら、そのユニークなストーリーと高い完成度で大きな注目を集めています。
監督・脚本・撮影・編集
主なキャスト
主演の山口馬木也さんの妻や家族情報、ブルーリボン賞受賞の裏側はこちらをチェック
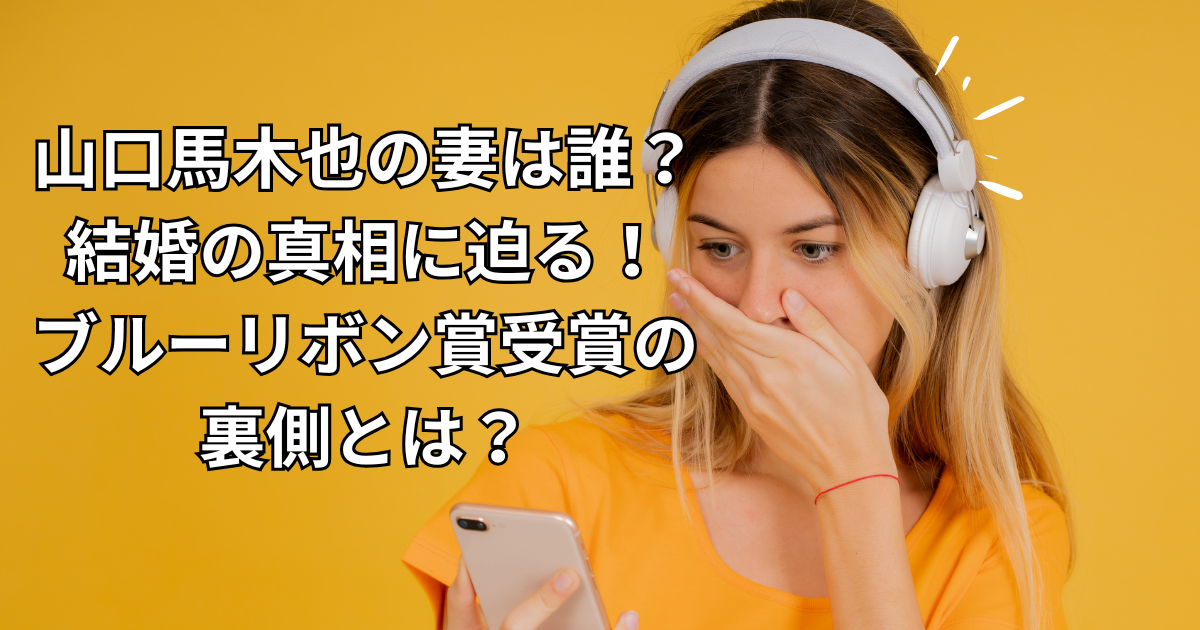
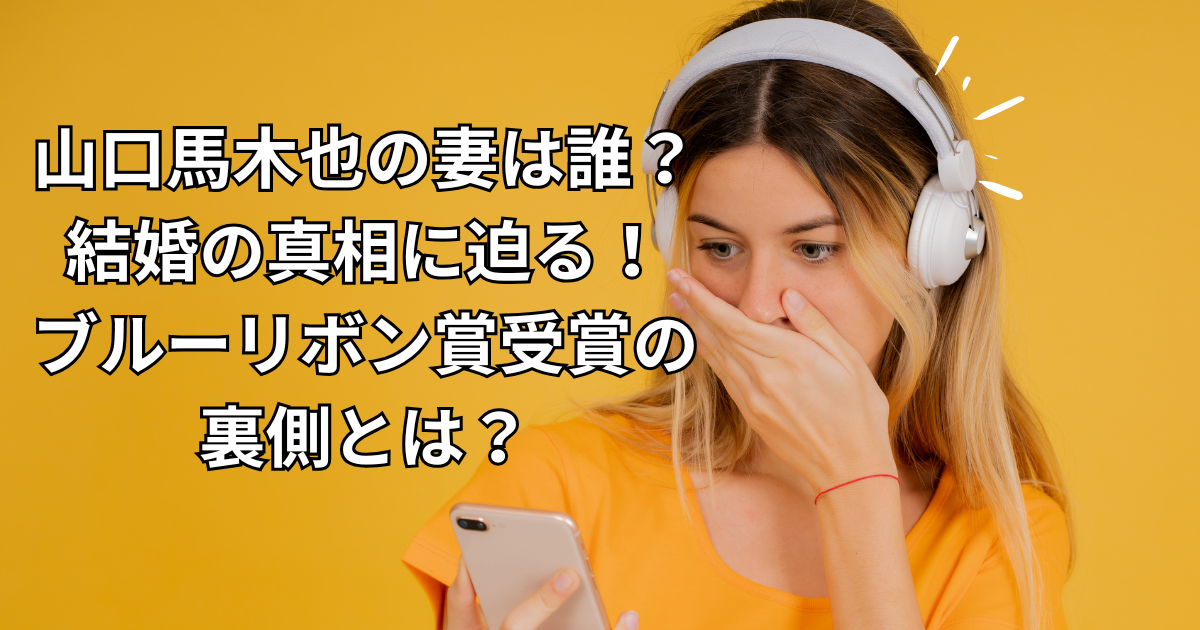
製作費
約2,600万円(うち2,000万円は監督の自費)
公開日
2024年8月17日
上映館数の推移
- 2024年8月17日:東京・池袋シネマ・ロサの1館で公開開始
- 2024年10月末:上映館数が283館に拡大
- 2024年11月中旬:さらに上映館数が増加し、348館に達する
興行収入の推移
- 2024年10月末:興行収入が5億円を突破。
- 2024年11月中旬:興行収入が約8億1,500万円に達する。
作品の特徴
本作は、低予算ながらも東映京都撮影所の協力を得て、本格的な時代劇の撮影が行われました。監督の安田淳一氏は、監督業のみならず、脚本、撮影、編集など多岐にわたる役割を一人で担い、制作スタッフも約10名と少人数での制作となりました。
「侍タイムスリッパー」のあらすじ(ネタバレなし)
まずは、「侍タイムスリッパー」のあらすじをネタバレなしで簡単に紹介します。
舞台は幕末の京都。会津藩士・高坂新左衛門(山口馬木也)は、藩を守るため、長州藩士を討つという密命を受けます。しかし、激しい戦いの最中、落雷に遭い、気を失ってしまうのです。
目が覚めると、そこは見たこともない場所で、周囲には高層ビルや奇妙な乗り物が溢れていました。新左衛門は、なんと現代の京都にタイムスリップしてしまったのです。
時代劇の撮影所という、奇しくも侍と縁のある場所にタイムスリップした新左衛門は、そこで「斬られ役」として働くことになります。
「侍タイムスリッパー」のあらすじ(ネタバレあり)



ここからは「侍タイムスリッパー」のあらすじをネタバレ有りで詳細にお伝えしていきます!映画館に行く前にネタバレしたくない方はご注意ください!!
幕末の京都。会津藩士・高坂新左衛門(山口馬木也)は、藩の密命を受け、長州藩士・山形彦九郎(庄野崎謙)を討つため、闇夜に身を潜めていました。しかし、刀を交える瞬間、突如雷鳴が轟き、落雷により気を失ってしまいます。


目を覚ますと、そこは見知らぬ場所。周囲には高層ビルが立ち並び、車や電車といった見慣れぬ乗り物が行き交っています。新左衛門は、現代の京都にタイムスリップしてしまったのです。彼は、江戸幕府がすでに140年前に終わったことを知り、愕然とします。
混乱の中、時代劇の撮影所に迷い込んだ新左衛門は、撮影中のスタッフや俳優たちを本物の敵と勘違いし、刀を構えて威嚇します。撮影機材を異国の武器と誤解し、斬りかかろうとするなど、騒動を引き起こします。その後、現代の街に飛び出した彼は、ポスターを見て自分が未来に来てしまったことを理解し、深い絶望感に襲われます。
途方に暮れる新左衛門は、心優しい西経寺の住職(福田善晴)とその妻・節子(紅萬子)に助けられ、寺に居候することになります。現代の生活に戸惑いながらも、持ち前の素直さと真面目さで徐々に適応していきます。ある日、テレビで時代劇を目にした新左衛門は、その迫力と演技に感銘を受け、「斬られ役」こそ自分にできる仕事だと考え、撮影所の門を叩く決意をします。


撮影所では、殺陣師の関本(峰蘭太郎)が率いる「剣心会」という斬られ役のプロ集団が活動しており、新左衛門は彼らに弟子入りを志願します。最初は戸惑いや誤解もありましたが、持ち前の剣術の才能を活かし、次第に斬られ役としての技術を磨いていきます。彼の真摯な姿勢と卓越した剣技は、周囲の人々の心を動かし、撮影所内でも一目置かれる存在となっていきます。
やがて、新左衛門の才能は時代劇の大スター、風見恭一郎(冨家ノリマサ)の目に留まります。風見は、新作映画で新左衛門を重要な役に抜擢します。しかし、驚くべきことに、風見の正体は、かつて新左衛門が幕末で斬り合った長州藩士・山形彦九郎でした。彼は新左衛門よりも20年早く現代にタイムスリップし、俳優として成功を収めていたのです。
再会を果たした二人は、時代劇の解釈や史実をめぐって対立します。新左衛門は、新作映画の脚本で故郷・会津藩の悲惨な末路を知り、大きなショックを受けます。そして、生き残った自分だけが時代に置いていかれたような、深い喪失感と罪悪感に苛まれることになります。
クライマックスでは、新左衛門と風見が、それぞれの思いを胸に、真剣を使った殺陣を繰り広げます。


この真剣を使った殺陣は、かつて映画「座頭市」の撮影中に起きた事故を彷彿とさせ、撮影所内では緊張感が高まります。物語は、新左衛門と風見の過去と現在が交錯する、手に汗握る展開へと進んでいきます。
「侍タイムスリッパー」の作品の魅力
「侍タイムスリッパー」は、単なるタイムスリップコメディ映画ではありません。幕末から現代にタイムスリップした侍という、奇想天外な設定でありながら、新左衛門の葛藤や成長、そして「侍の魂」を通して、現代社会に生きる私たちに大切なメッセージを投げかけています 。
新左衛門の成長物語
タイムスリップによって何もかも失った新左衛門は、当初は絶望の淵に立たされます。しかし、心優しい人々との出会いを通して生きる希望を取り戻し、斬られ役という仕事を通して、現代社会で生き抜く力強さ、そして侍としての誇りを持ち続ける姿は、多くの人の心を打ちます 。
例えば、新左衛門が初めて携帯電話やコンビニエンスストアを目にした時の驚きよう、そして斬られ役の稽古に真剣に取り組む姿は、彼の純粋さと真面目さを際立たせています。
時代を超えた価値観の対立と調和
新左衛門と山形、異なる時代を生きる二人の侍の対立と和解は、異文化理解の重要性を示唆しています 。互いの立場や信念を理解し、尊重し合うことの大切さを、彼らの姿を通して学ぶことができます。
時代劇への愛
かつては隆盛を極めた時代劇も、現代では斜陽産業と言われています 。そんな時代劇の世界で、それでもなお情熱を燃やし、作品作りに励む人々の姿は、時代劇ファンならずとも感動を覚えます。
侍の精神
この映画は、侍を単なる「強い」「刀を使う」といったステレオタイプなイメージで描くのではなく、変化への対応力や、どんな状況でも自分の信念を貫く心の強さといった、現代社会でも通じる侍の精神を描いています 。新左衛門は、斬られ役という、侍のプライドを傷つけかねない仕事でさえ、真摯に受け止め、その中で自分の存在意義を見出していきます。
個性豊かな登場人物
新左衛門を支える住職夫婦や、ヒロインの山本優子など、魅力的な登場人物たちが物語を彩ります 。彼らの温かさは、新左衛門の心の支えとなり、物語に深みを与えています。
斬新な撮影手法
時代劇の殺陣シーンでは、「マトリックス」のような斬新な撮影技術を導入し、リアリティあふれるアクションシーンを作り出しています 。
「侍タイムスリッパー」のレビュー・感想



「侍タイムスリッパー」は、多くの映画ファンから高い評価を得ています!!
笑いと感動
単なるコメディ映画ではなく、新左衛門の心の葛藤や成長、そして人との繋がりを描いた人間ドラマとしても高く評価されています。
役者の演技力
主演の山口馬木也さんをはじめ、ベテラン俳優から若手俳優まで、役者陣の熱演が光ります 。特に、山口馬木也さんは、時代劇で培った殺陣の技術と、繊細な感情表現で、新左衛門という複雑な役を見事に演じ切っています。この好演が認められて2025年第67回ブルーリボン賞では主演男優賞を受賞しました!
時代劇の素晴らしさ
時代劇ならではの魅力である、武士道精神や、人間同士の義理人情を、現代社会に生きる私たちに改めて思い出させてくれる作品です。
丁寧な作品作り
自主制作映画とは思えないほどの完成度の高さに驚きの声が上がっています 。限られた予算の中で、脚本、演出、演技、そして時代劇の再現性など、細部にまでこだわった作品作りが評価されています。
侍タイムスリッパ―の監督・制作陣について
「侍タイムスリッパー」は、安田淳一監督による自主制作映画です 。安田監督は米農家と油そば屋を兼業しながら
また、助監督役の沙倉ゆうのは、実際の助監督も務めており、彼女の母親も小道具の刀の整備などを手伝うなど、家族ぐるみで制作に携わっています 。
まとめ
「侍タイムスリッパー」は、時代劇への愛と、現代社会へのメッセージが込められた、エンターテイメント性と社会性を兼ね備えた作品です。
斬られ役という仕事を通して成長していく侍の姿は、私たちに勇気を与え、時代を超えた価値観の対立と調和は、異文化理解の大切さを教えてくれます!!



「カメラを止めるな!」のように 、口コミで評判が広がり、異例の大ヒットを記録したことも、この映画の魅力を物語っています。
まだご覧になっていない方は、ぜひ劇場に足を運んでみてください!